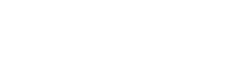SSHインドネシアサイエンス研修4
インドネシアサイエンス研修5日目
本日も本校の連携校であるペトラ高等学校グループとの交流を実施しました。
※ペトラ高等学校グループと本校は連携校として協力をしていくために協定書を交わしています。
※本校は姉妹校以外にこうした形で海外にいくつかの連携校があります
5日目はPetra Acityaという学校で交流を行いました。
まず、スクールツアーを実施していただきました。グループの中では新しい学校なので、非常にきれいで充実した設備を見学させていただきました。ICT機器もそろっており、グループディスカッションからそのままスライド資料を使ったプレゼンを行うことも簡単にできる学校です。
次に、本校教諭によるGPGPというプログラムを行いました。GPGPは、Great Pacific Garbage Patchを省略したもので、太平洋に浮かぶゴミの一帯について、防止策と改善策をグループでディスカッションしました。ディスカッションで出た様々な意見をまとめ、グループごとにプレゼンテーションを行いました。
<プレゼン内容の一例>
◯バイオプラスチックの活用
◯AIを活用し、プラスチックを追跡し集めるロボットを製作
〇教育の充実
〇プラスチックを回収しガソリン(燃料)を合成する
教育の充実については、看板を「ゴミをここにすてるな」から「ポイ捨てすると海にいく」にすることで、より深く考えさせることができるのではないかという意見が出されました。
プラスチックを回収については、プラスチックから燃料を合成できれば、海に漂うプラスチックはごみではなく資源に変わり、回収が加速していくのではないかという意見が出されました。また、資源となったプラスチックをそもそも海へ放出しなくなるのではないかという意見が出されました。
それぞれのアイデアをプレゼンする場面では、漢字をシンボルとした看板を考えたグループもあり、資源をどのように循環させるかということを「再」の一文字で表していました。
最後に、お礼も兼ねて本校教諭主催の「日本の伝統的な遊び」をペトラ高校の生徒に体験してもらいました。お手玉、けん玉、羽子板などに挑戦をしてもらいながら、交流をしました。なお、これらは本校ではスポーツサイエンス的な位置づけで動作解析アプリを使用して研究をしたこともあります。
両校の関係を維持しながら、サイエンス的な取組を通じて環境について深く考えることで、またそれをSDGsとも関わらせて地球環境について深く考えることで、引き続きグローバルサイエンスリーダーの育成をしていきたいと思います。