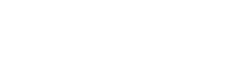人権教育講演会「私たちの性の多様性について」を実施しました
人権教育講演会「私たちの性の多様性について」を実施しました
10月8日(水)に人権教育講演会を実施しました。
今年度は、埼玉大学ダイバーシティ推進センター准教授の渡辺大輔さんに講師として来ていただき、性の多様性という視点から人権について講演をしていただきました。講演は、単純な文章の並べ替え問題から始まりました。並べ替えると、「父と息子が交通事故に遭い、治療にあたった外科医が『これは私の息子!』と叫ぶ」というストーリーが完成します。ここで渡辺さんは生徒たちに、「人物の関係が分からなくなった人はいないか」と問いかけました。多くの生徒が手を上げる中、渡辺さんはいくつかの考え方の例を紹介してくださいました。「父とは育ての親で、外科医とは生みの親である」「外科医は母親である」「外科医はゲイで、父はそのパートナーである」などなど。外科医が母親という可能性を知らず知らずのうちに排除していたことに気付き、渡辺さんがおっしゃるジェンダーバイアスが自分にあることを思い知りました。
また、「女なんだから…」「男なんだから…」「女らしい!」「男らしい!」――「らしさ」を他人に求め、押し付けることの危険性を渡辺先生は指摘していらっしゃいました。体の性別は男と女の二つですが、性自認・性的指向の組み合わせを考えると、少なくとも24通りあるということを紹介いただき、生徒のみならず教員も、私たちの性がいかに多様であるかを知ることができました。
映像を通して多様性と包摂について考える時間もありました。映像には、特殊な電光板に表示される人の骨が。その電光板の裏からは、様々な人種・宗教・性・国籍・年齢の人々が登場します。渡辺さんは「(人種などが異なっていても)骨になってしまえば皆同じ。博愛・友愛・家族愛と様々あるが、愛は愛なのです」と補足していらっしゃいました。
最後に、教員・生徒向けに、紙をちぎるワークをご用意いただきました。渡辺さんの指示に従って、各々が紙を折ったりちぎったりしていきます。全員が同じ指示に沿って活動しているはずなのですが、紙をひろげてみると、同じ形の紙は一つとしてありませんでした。異なる形の紙は、私たちそのものだったのです。多数派の作る「フツー」に慣れた私たちにとって、非常に貴重なお話でした。この機会を契機に、多様な私たちが、互いを認め合える雰囲気づくりを一層進めていきたいと考えています。